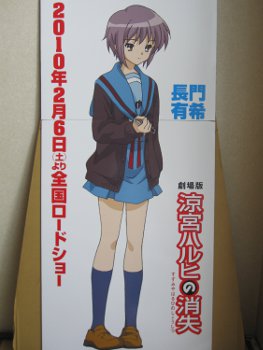
映画「涼宮ハルヒの消失」のPOP(立て看板)。らっきー☆れーさー![]() 第1期の景品。来るとは思わなかった。近くで見るとすごい解像度低い(ドット数の少ないCGを無理に引き伸ばしてある)のですがorz
第1期の景品。来るとは思わなかった。近くで見るとすごい解像度低い(ドット数の少ないCGを無理に引き伸ばしてある)のですがorz
らっきー☆れーさーというのは、2010年4月から毎週計10回放送されたらき☆すたスピンアウト企画。個人的には以下に書くように失敗感漂う感じで終わったのですが、これ書くためにHP見直したら予想外の第2期開始w
第1期のルールはうろ覚えですが、- カートで勝負、1位になった人だけその人が推す商品を広告できる。
- 番組パーソナリティである白石稔さんが勝ったときは京都アニメーション
 の商品宣伝。
の商品宣伝。 - 声優ほかアニメ関係のゲスト参戦もあるよ!
白石稔以外は京アニスタッフしかいねぇ
これ誰が勝っても京アニ商品の宣伝じゃないか。オープニングが「第1回目から雨!」で始まったので、「雨女の今野さん来たのか!?」と期待したのにねぇorz 第2レースも同じレース場ってことは同じメンバーで2回撮り。なんだかなぁ。そんな感じで固定メンバーで回を重ね、毎回京アニ商品の宣伝。レースの意味が感じられない状態でした。う~ん、広告希望者がいないのだろうか。
広告主が付きゲスト参戦者が現れれば状態が変わるかなと思っていた中、第5回に水原薫さん(日下部みさお役)がゲスト参戦。お、これで状況が変わるかなと思ったのですが、逆に現在のルールの欠陥に気づかされました。- ハンデを貰っても水原さん完敗
- レギュラー陣、過去数回のレースで上達してまして、初心者の水原さん歯が立たず。アニメ関係者でカートが上手いなんて人、かなり敷居高いでしょう。ゲストを立てて勝たせようものなら出来レースにも取られかねないわけで、ゲストが商品紹介する機会は高くない。
- 1位にならないと宣伝できない
- 宣伝してもらえない確率が高いなら、広告主も手が出しにくくないかなと。類似した企画の熱湯コマーシャル
 は時間の違いはあれど宣伝はできたわけで、まったく宣伝できないでは旨みが無い。無料で宣伝させてくれるならまだ挑戦する気になるかもしれないけど、新感覚の「商品紹介番組」なわけでして、広告費取るだろ?
は時間の違いはあれど宣伝はできたわけで、まったく宣伝できないでは旨みが無い。無料で宣伝させてくれるならまだ挑戦する気になるかもしれないけど、新感覚の「商品紹介番組」なわけでして、広告費取るだろ?
ちなみに次のレースで水原さん勝ちましたが、京アニ商品の宣伝でしたorz
苦境に立たされた番組には付き物のマイナーチェンジを繰り返しながら回を重ね、たどり着いたのは、- F1よろしく順位に応じてポイントをレーサーに付与、累計ポイントを争う形式。事実上のゲスト参戦者廃止ですね。
- さらに視聴者にある時点での累計ポイント順位クイズを提供、正解者にはプレゼント。
で。直前まで気づかなかった私も馬鹿ですが、応募締め切りが全レース終了後だったんですね。しかもご丁寧にWeb上では毎レースの結果と累計ポイントを掲載。ほとんどヒントとして下に答えが書いてある懸賞クイズの状態w さすがにこんなクイズ、当選者5名だし当選は期待できないと思いつつ応募したら、当たってしまったというお話でした。運がよかったのか応募者が少なかったのか、悩むところ。
私の考えていた番組の欠点がある程度は当たっていたのか、2010年7月から始まった第2期は順位に応じて秒数が違うながらも全商品紹介など修正がされてきたようです。ただ疑っちゃキリ無いんだけど、最初から各商品の秒数決まっててレース後に誰が何を紹介するか割り当てても分からないんだよねぇ。どうせなら、各レーサーに広告主を結び付けておいて「毎回紹介時間が短いって怒られた」とか内情暴露ネタ入れたほうが面白いかなと思ったり。 商品紹介とポイント争奪戦のレースを分けた(2レース開催)ようです。というわけで、動画配信のある商品紹介レースは(凶悪なハンデなど)脚色OK、ゲストカモ~ンですね。
ちなみに第2期も同様のクイズがありまして、締め切りは全レース終了後です☆








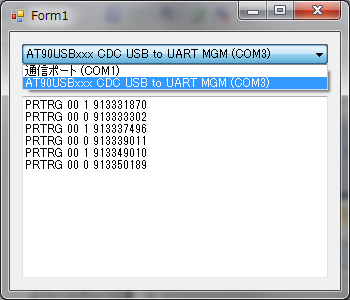

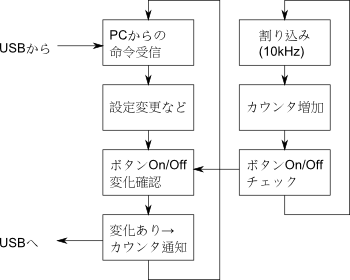
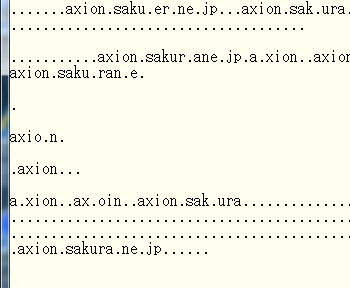
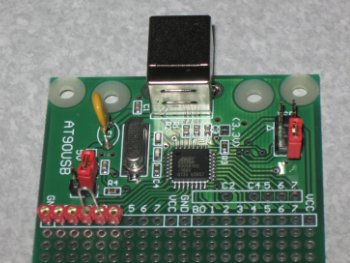







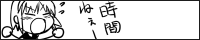
Comments